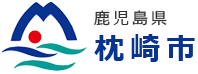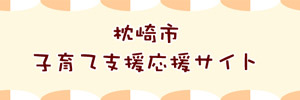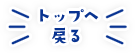本文
外来生物「オオキンケイギク」及び「メリケントキンソウ」について
オオキンケイギクとは
 |
 |
|---|---|
| オオキンケイギクの花と葉「写真提供:九州地方環境事務所」 | |
オオキンケイギクは北米原産の多年草で、5月~7月にかけて黄色の花を咲かせます。高さは30cm~70cm程度で、かつては道路の法面緑化に使用されたり、苗が販売されたりしていました。しかし、繁殖力が強く生態系に悪影響を与えるおそれがあるとして、2006年2月1日に「特定外来生物」に指定されました。特定外来生物は、栽培・運搬・保管・輸入・譲渡・野外に放つことなどを許可無く行うことが禁止されています。きれいな花だからといって持ち帰ったり、栽培しないように注意してください。
オオキンケイギクを発見したら
オオキンケイギグが庭などに生えているのを見かけたら、根から抜き取るか、地際で刈り取るようにして駆除するようにしてください。また、生育場所によっては除草剤での駆除も有効です。駆除の時期としては、種子がつく前(5~7月)が適しています。しかし、オオキンケイギグは生きたまま移動させる、保管するなどの行為が禁止されています。処理する際には、根から引き抜いたものを2~3日天日にさらして枯死させる等した後で、「燃えるごみ(緑の指定ごみ袋)」として出してください。
・オオキンケイギクに注意しましょう(九州地方環境事務所のホームページ)<外部リンク>「提供:九州地方環境事務所」
リンク先下部に九州地方環境事務所作成のオオキンケイギクのチラシがありますのでご覧ください。
メリケントキンソウとは
 |
 |
|---|---|
| メリケントキンソウの葉と果実のトゲ「写真提供:環境省奄美野生生物保護センター」 | |
南米原産の一年草(発芽後一年間で種子をつけ、その後枯れてしまう植物)で、1930年代に和歌山県で初めて移入が確認されました。 4~6月に硬いトゲを持った種子をつけることが知られており、この種子が靴底などに刺さることで人為的に運ばれ、生息地が拡大していきます。特に公園や芝生など日当たりのよい場所を好んで生息します。特定外来生物には指定されていませんが、硬いトゲを持った種子をつけるため、公園等の利用者がけがをすることが懸念されています。
メリケントキンソウを発見したら
開花時期(2~3月)に抜き取りや生育場所によっては除草剤での駆除も有効です。
刈り払い機による駆除は、種子を拡散させ、残った節からも発芽して成長するので注意が必要です。
・メリケントキンソウに注意しましょう(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>
・メリケントキンソウ駆除マニュアル(著作:鹿児島県外来動植物対策推進員窪健一氏)[PDF:428KB]<外部リンク>
その他の外来種について
・県内外来種(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>